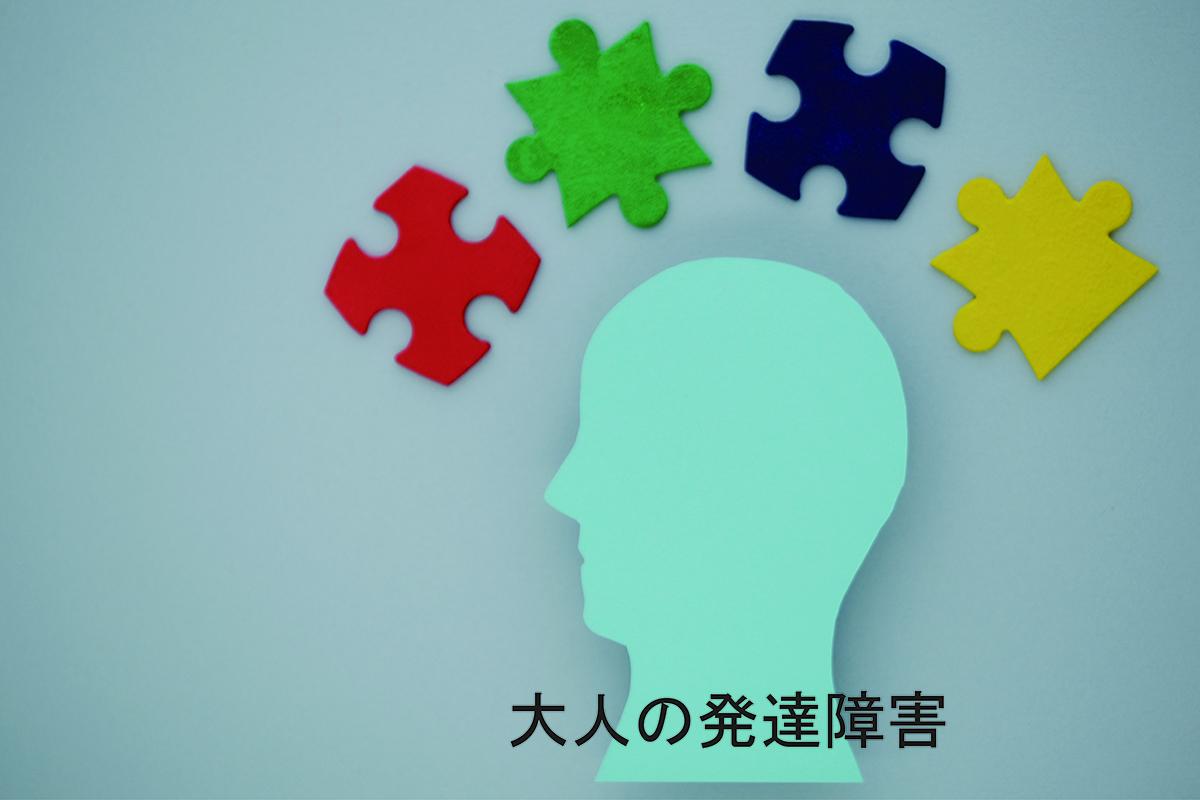離職率の低下や生産性の向上につながるワークエンゲージメントとは?
- 産業保健

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対してポジティブな感情を持ち、充実している状態を指します。企業がワークエンゲージメントの向上に取り組むことで、離職率の低下や生産性の向上などの効果が期待できます。本記事で詳しく解説していきます。
おすすめの資料
ワークエンゲージメントとは?

ワークエンゲージメントとは?
ワークエンゲージメントとは、仕事に対する前向きで充実した心理状態を指す概念で、オランダ・ユトレヒト大学のSchaufeli教授らによって提唱されました。従業員が仕事に深く関与し、活力に満ち、意欲的に取り組んでいる状態を表します。日本では、厚生労働省の「令和元年版労働経済白書」においてもその重要性が取り上げられ、生産性向上やメンタルヘルスの観点から注目されています。
ワークエンゲージメントには、以下の3つの要素が含まれます。
- ●活力(Vigor)
- 高いエネルギーと精神的な回復力を持ちながら、困難な仕事にも粘り強く取り組む状態のことを指します。
- ●没頭(Absorption)
- 仕事に夢中になり時間を忘れるほど没頭している状態で、没頭した状態が持続すると問題が起きにくくなり、業務の正確性、生産性の向上につながります。
- ●熱意(Dedication)
- 仕事に誇りや意味を感じ、やりがいや情熱を持って取り組んでいる状態です。仕事に対して積極的で、困難にも前向きに取り組む姿勢を表します。
ワークエンゲージメントは「やる気」や「モチベーション」とは異なり、より深いレベルでの関与とエネルギーの投入を意味します。ワークエンゲージメントが高い従業員は、業務パフォーマンスが高く、離職率も低いとされており、組織全体の健全な成長にも寄与するとされています。
参考:厚生労働省 令和元年版 労働経済の分析−人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について−
ワークエンゲージメントに関連する概念
- ●バーンアウト
- バーンアウトは、慢性的な仕事上のストレスにより、心身の疲労や意欲の喪失が生じる心理状態を指し、燃え尽き症候群とも呼ばれています。 バーンアウトの主要な構成要素は以下のものがあります。
-
- ・情緒的消耗感(Emotional Exhaustion):エネルギーが枯渇したような疲労感
- ・脱人格化(Depersonalization):仕事相手への冷淡さや否定的な態度
- ・個人的達成感の低下(Reduced Personal Accomplishment):自己肯定感の減少
ワークエンゲージメントはバーンアウトと対極関係にあり、高いエンゲージメントの場合には、低いバーンアウト傾向になります。
- ●ワーカーホリズム
- ワーカーホリズムとは、過度に仕事に依存し、自己の生活の多くを仕事に費やしてしまう状態を意味します。「働きすぎ」や「働かないと罪悪感を覚える」など、プライベートの犠牲や健康被害を招くこともあります。ワークエンゲージメントもワーカホリズムも仕事に没頭する状態ではありますが、ワークエンゲージメントが自発的なポジティブな感情によるものである一方、ワーカホリズムは強制的で義務感に駆られて働くネカティブでストレスフルな状態であるという違いがあります。
- ●職務満足感
- 職務満足感は、仕事そのものや職場環境、報酬、人間関係などに対する全体的な満足感や快楽の感情を意味します。職務満足感は、仕事のやりがい、成長の実感、仕事の意義、給料、職場の人間関係、職場環境に影響されます。職務満足感は仕事のアウトカム的なものであり、満足しているからといって必ずしも高いパフォーマンスを発揮するとは限りません。一方、ワークエンゲージメントはプロセス中の心理状態を指しており、高いエンゲージメントは高パフォーマンスにつながりやすいという違いがあります。
従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い
従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とワークエンゲージメント(Work Engagement)は似た言葉ですが、定義や尺度、測定方法、目的において明確な違いがあります。
- ●ワークエンゲージメント
- 個人が仕事に対して抱くポジティブで充実した心理状態
- ●従業員エンゲージメント
- 従業員が組織や上司・会社全体に対して抱く心理的な愛着や忠誠心で、評価者は経営層や人事
ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントは焦点が異なる概念であるものの、両者は相互に影響を及ぼし合い、従業員が組織に信頼や誇りを持つと、仕事への情熱や意欲が高まりやすくなります。一方で、日々の業務に充実感を得ることで、組織への愛着や定着意識が強まることもあります。両者をバランスよく高めることが、持続的なパフォーマンスと定着率向上につながります。
ワークエンゲージメントの尺度と測定方法

従業員のワークエンゲージメントを把握する方法には次の3つの方法があります。
ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント(Utrecht Work Engagement Scales:UWES)
UWESは、ワークエンゲージメントの測定法の中で最も広く使用されている心理尺度の一つで、オランダの心理学者Arnold B. BakkerやWilmar B. Schaufeliらによって開発されました。この尺度は、ワークエンゲージメントの構成要素である「活力(Vigor)」「没頭(Absorption)」「熱意(Dedication)」の3次元を測定するために設計されており、各項目に対し7段階リッカート尺度(例:0=まったくあてはまらない〜6=非常によくあてはまる)で回答し、各次元の平均点、または全体の平均点を算出して評価します。高スコアであるほどワークエンゲージメントが高い傾向があります。
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory - General Survey)は、バーンアウト(燃え尽き症候群)を測定するために最も広く用いられている心理尺度で、心理学者Christina Maslachらによって開発されたMaslach Burnout Inventory(MBI)のバージョンのひとつです。MBIは医療・教育・福祉などの燃え尽き症候群が多い職業の評価として開発されましたが、MBI-GSは一般職種に従事するすべての労働者を対象とした汎用的なバーンアウト尺度になっています。全16項目からなり、MBI-GSの高スコアはワークエンゲージメントの低下と相関が見られることがわかっています。
OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)
MBI-GSと同様にバーンアウトの測定に用いる尺度で、ドイツの心理学者 Evangelia Demerouti らによって開発されました。汎用性が高く無料で使うことができるため、学術研究や企業内調査でも利用しやすいのが特徴です。
ワークエンゲージメントを高める要因

ワークエンゲージメントを高めるためには、「仕事の資源」と「個人の資源」を充実させることが大切です。
仕事の資源
ワークエンゲージメントを高める要因として、特に重要とされるのが仕事の資源(Job Resources)です。
仕事の資源とは、業務の効率化をはかり、業務負担から生じる過度なストレスを軽減して、モチベーションを高めるための要素で、自分ではなく外部から影響を与えられるものです。例として以下のようなものがあります。
(例)
- ・正当な評価
- ・仕事の裁量権
- ・上司や同僚からのサポート
- ・仕事に対する適切なフィードバック
など
正当な評価は熱意や達成感の促進につながり、エンゲージメントを直接高めることができます。仕事の資源は、エンゲージメントを高めるカギであり、単にストレスを軽減するだけでなく従業員がポジティブに、意欲的に働くために必要な要素です。企業やマネージャーが、こうした資源を意図的に設計・提供することが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
個人の資源
個人の資源とは、従業員が仕事に前向きに取り組むための内面的な強みや心理的能力のことです。例として以下のようなものがあります。
(例)
- ・楽観性
- ・自己効力感
- ・ポジティブ思考
- ・レジリエンス(困難から立ち直る力)
- ・希望
など
これらの仕事に前向きに取り組むための内面の強みや心理的能力は、仕事の資源と並んでワークエンゲージメントを高める強い要素となります。
企業ができる取り組み
仕事の資源を高めるための具体的な方法として次のようなものがあります。
- ・上司・同僚からのサポートを強化:定期的な1on1ミーティングの実施で信頼関係を構築し、仕事の悩みなどについて話せる場を作る
- ・成長機会・スキル開発の提供:社内研修や外部セミナー、キャリア面談などスキルアップのための機会を提供することで、従業員が成長を感じられる環境を整える
- ・仕事の自立性と裁量:従業員が自ら仕事の進め方や、目標を立てられるようにすることで、責任感や主体性が高まる
- ・柔軟な働き方の整備:フレックスタイム制度や在宅勤務などを導入し、時間や場所に対する裁量を持たせる
また、個人の資源を高めるための方法としては、以下が挙げられます。
- ・ロールモデルを持つ:尊敬できる上司や同僚の行動を観察し、「自分だったらどうするか」など主体性や自立性を養う
- ・フィードバックを受ける:上司や同僚からのポジティブなフィードバックを受けることで、自らの仕事に対して自信を持つことができる
- ・メンタルヘルスケア:ストレスチェックや産業医面談を定期的に行うことで、従業員の心理的負担を軽減することができ、心身の健康によって個人の資源の充実につなげることができる
これらの取り組みを通じて従業員のワークエンゲージメントが向上すれば、それは企業全体の成果に直結します。したがって、企業側がこれらの取り組みを実施する意義は非常に大きいと言えます。
企業の健康経営を促進し、持続的な成長と成功を実現するためにも、ワークエンゲージメントを高める取り組みを積極的に行いましょう。
まとめ:ワークエンゲージメントの向上で、強い組織を築く!
ワークエンゲージメントが高い職場では、離職率の低下、職場の雰囲気の改善、チームの協働力向上といった好循環が生まれます。ワークエンゲージメントは単なる個人のモチベーションではなく、企業の持続的な成長をする基盤です。ワークエンゲージメントの向上を目指して積極的に取り組んでいきましょう。
おすすめの資料