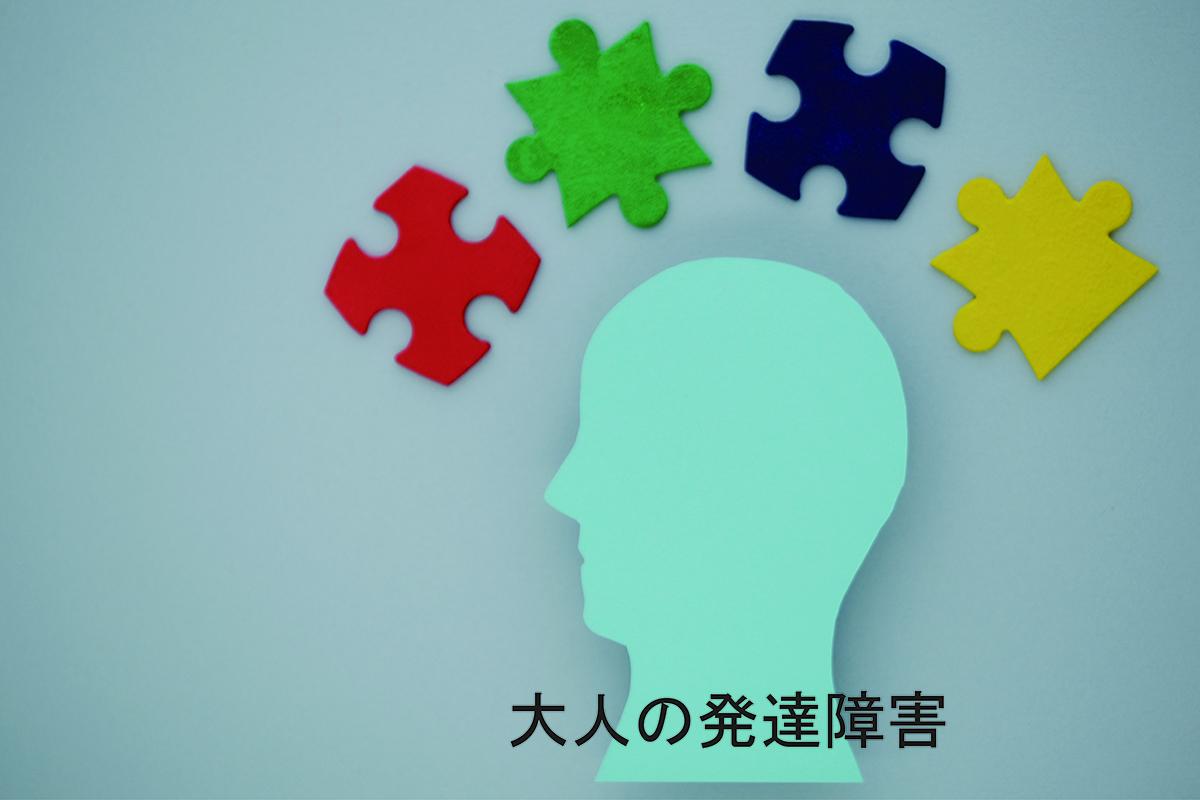【障害者差別解消法】職場における合理的配慮とは?
- 産業保健

障害者差別解消法をご存知でしょうか?障害の有無に限らず、共に生きる社会の実現を目指して制定されたのが障害者差別解消法です。令和6年4月1日に改正法が施行され、職場でも障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。職場における合理的配慮とはどのようなものなのか、詳しく解説していきます。
おすすめの資料
障害者差別解消法における合理的配慮の提供

障害者差別解消法の概要
障害者差別解消法は障害のある人への差別をなくし、障害の有無に関わらず共に生きる社会の実現を目指すための法律で2013年に制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対し、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供を義務づけています。
障害者差別解消法で定める「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害がある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次機能障害を含む)など、障害や社会の仕組みなどによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象です
参考:政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」
【障害者差別解消法】不当な差別的取り扱いとは?
不当な差別的取り扱いとは、障害を理由として、障害がない人とは異なる不利な扱いをすることです。
たとえば、「障害のある方の入店はお断りです」など正当な理由なしに入店を拒否する行為や、障害があることを理由に、障害がある人に対し一律に接遇の質を下げる行為、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為などが不当な差別的取り扱いにあたります。障害者差別解消法ではこれらの不当な差別的取り扱いを禁止しています。
参考:政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」
【障害者差別解消法】合理的配慮の提供とは何か?
障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供は、障害のある人から日常生活や社会生活を送るうえで、「社会的なバリアを取り除いて欲しい」との意思が示された際に、過重な負担にならない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることと定義されています。
2021年に障害者差別解消法が改正され、企業や学校、病院、商業施設などの民間事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されました。2024年4月1日に施行された改正障害者差別解消法において、合理的配慮の提供は、あくまで「過重な負担にならない範囲で」行うことが前提となっています。費用面や人員、設備の問題などで現実的に不可能と判断される場合には、除外されます。ただし、その場合も企業側が一方的に拒否するのではなく、本人との対話を通じて、できる範囲の対応を検討する必要があります。
合理的配慮の事例

内閣府の合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)は、障害者差別解消法に基づき、障害のある人が社会参加しやすくするための「合理的配慮の提供」や「環境の整備」の事例を、関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集・整理したものです。以下、いくつか事例を紹介します。
障害の種別による配慮
- ●視覚障害
-
- ・資料を拡大文字や点字で作成し、資料の内容を読み上げて伝える
- ・パソコン等の音声読み上げ機能を使えるように整備する
- ・本人の意思をしっかりと確認したうえで、書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する
- ●聴覚・言語障害
-
- ・筆談、手話、コミュニケーションボードなど目で見て分かる方法で意思疎通を行う
- ・市役所や銀行などの窓口において、順番を知らせる場合は、アナウンスだけではなく身振りなどによってしっかりと相手に伝わるようにする
- ●肢体不自由
-
- ・車椅子利用者のために段差に携帯型のスロープを渡す
- ・脊髄損傷などによって体温調整機能が損なわれている場合には、エアコンなどの室温調整に配慮する
- ●精神障害
-
- ・情緒不安定になりそうな時は、別室などの落ち着ける場所を提供する
- ・情報が曖昧な場合や、一度に複数の情報を伝えると混乱に陥りそうな時には、具体的な内容を提示し、優先順位を示す
など
生活の場面における配慮
- ●雇用・就業での配慮
-
- ・業務指示や連絡に際して、筆談やメール等を利用する
- ・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行う
- ・感覚過敏を緩和するためのサングラスの着用や耳栓の使用、体温調整しやすい服装の着用を認めるなどの対応を行う
- ・本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整する
- ●聴覚・言語障害
-
- ・筆談、手話、コミュニケーションボードなど目で見て分かる方法で意思疎通を行う
- ・市役所や銀行などの窓口において、順番を知らせる場合は、アナウンスだけではなく身振りなどによってしっかりと相手に伝わるようにする
- ●サービス(買物、飲食店など)での配慮
-
- ・段差がある場所などは補助したり、高いところにある商品などは取って渡したりする
- ・メニューや商品表示を分かりやすくし、写真を活用して説明する
- ・金額がはっきり分かるように、レジや電卓の表示板を見やすいように相手に向けたり、紙などに書いたりして示すようにする
- ●医療・福祉での配慮
-
- ・車椅子の利用者が使いやすいようにカウンターの高さを調整する
- ・院内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする
など
企業における合理的配慮の実施ステップ

企業が障害のある社員や求職者に対して合理的配慮を提供する際には、以下の4つのステップに沿いつつ、柔軟な対応が求められます。
STEP1.障害のある当事者からの申し出
障害のある人が、職場において何らかの困難に直面した際に、合理的配慮を求める意思表示を行います。その際、企業側の対応としては以下の点を事前に準備しておきましょう。
- ・相談窓口や相談体制の整備(人事・上司・産業医など)
- ・本人が申し出やすい環境づくり(個別面談・オンライン申請も含む)
- ・必要に応じて障害の特性を把握する(ただし本人への事前説明は必要)
STEP2.配慮内容について、当事者と「建設的対話」を重ねる
本人が感じている困難や希望を正しく理解し、業務のバランスなどを考えながら、調整可能な支援内容を話し合いましょう。「建設的対話」とは社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、双方向の対話を通じて合意形成を目指すことです。本人の意見を尊重しつつ、現実的な範囲での対応を検討し、代替手段の提案、職場環境や業務内容との整合性を考慮するようにしましょう。
STEP3.合理的配慮の確定と実施
対話をもとに具体的な配慮内容が決定されたら、速やかに実行に移します。例としては配慮内容を文書で記録し労使間で誤解を防ぐ、配慮内容に応じて現場担当者・同僚にも周知する、ICT機器、設備、勤務制度などの準備を行うなどが挙げられます。
STEP4.経過モニタリングと評価の実施
実際に実施している配慮が現場で効果を上げているかを継続的に確認し、必要に応じて見直しましょう。定期的な面談で業務の進捗・心身の状態の確認、障害の状況の変化がないかどうかは産業医面談等を活用するのも効果的です。人事や上司だけではなく、積極的に産業医の協力を求めましょう。
まとめ: 誰もが気持ちよく働ける職場環境づくりを
職場における合理的配慮の提供は、障害のある人が他の社員と平等に働くために、職場環境や業務の進め方を個別に調整することを求めるものです。決して「特別扱い」ではなく、働く機会の平等を実現するための工夫です。職場での理解と対話を通じて柔軟に対応することで、障害の有無に関わらず、誰もが気持ちよく働ける環境づくりを目指しましょう。
おすすめの資料