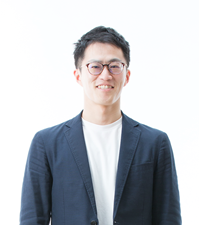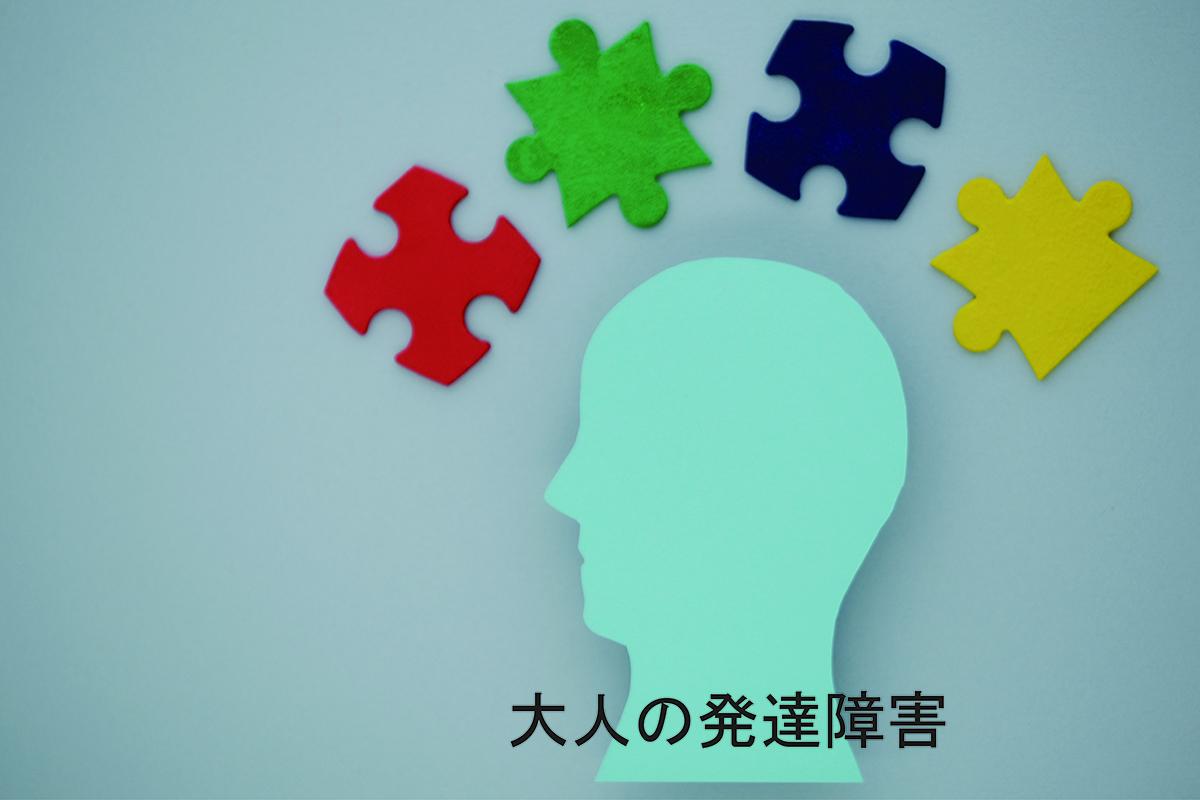熱中症対策の義務化とは?2025年6月からの変更点を解説

2025年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者は熱中症の重篤化リスクが高い職場において対策が義務付けられました。
労働者の体調不良を報告する体制の整備や、緊急時の応急処置に関する手順の作成・周知が義務化されています。
参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
2025年6月1日から何が変わるのか
今回の法改正における最大の変更点は、客観的な指標である「暑さ指数(WBGT)」に基づき、事業者が講ずべき具体的な措置が法的に義務付けられたことです。
具体的には、作業場所のWBGT基準値(※)を超える場合に、主に以下の3点が新たに義務化されました。
- ● 作業を中断し、休憩時間を十分に確保すること
- ● WBGT値を低減させるための設備を稼働させること
- ● 労働者の健康状態を随時確認すること
これらに加え、これまで努力義務とされてきた「労働者が体調不良を気軽に報告できる体制の整備」や「緊急時の応急処置に関する手順の作成・周知」も、このWBGT基準管理と一体のものとして、より確実に実施することが求められます。
形式的に手順書を作るだけでなく、全従業員が内容を理解し、緊急時に機能する状態への整備が必須になりました。
(※WBGT基準値の例:屋内31℃、屋外で中等程度の作業を行う場合28℃など、作業内容に応じて定められています)
なぜ対策が義務化されたのか?背景にある深刻な労働災害
対策が義務化された背景には、職場における熱中症による労働災害が後を絶たないという深刻な現状があります。
厚生労働省の統計によると、職場での熱中症による死傷者数は依然として高い水準で推移しており、多くの労働者が命の危険に晒されているのです。
熱中症による労働災害が後を絶たない状況を受け、国は事業者に対してより厳格な対策を求めることを決定しました。義務化は、すべての職場で実効性のある対策を講じさせるための、国からの強いメッセージといえるでしょう。
参考:厚生労働省「2024 年(令和6年) 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値) 」
義務化の対象となる事業者と職場環境の基準
今回の義務化は、原則として全ての事業者が対象となります。
特に、厚生労働省が定める暑さ指数(WBGT)の基準値を超える可能性がある暑熱な職場では、より厳格な対応が求められます。
具体的には、WBGT値を測定し、その結果に基づいて作業計画を見直すなど、客観的な指標に基づいた管理が必須です。建設業や製造業の作業場はもちろん、空調設備のない倉庫や厨房なども対象に含まれるため注意が必要です。
参考:熱中症予防情報サイト(環境省)「暑さ指数とは?」
知らないと危険!対策を怠った場合の罰則と3つの企業リスク

熱中症対策の義務を怠った場合、労働安全衛生法に基づき懲役または罰金が科される可能性があります。
また、生産性の低下、企業イメージの毀損、民事上の損害賠償といった、罰金以上に深刻な経営リスクにも直面する懸念もあります。
- 3つの経営リスク
-
- ● 経営リスク①:生産性の低下
- ● 経営リスク②:企業イメージの低下
- ● 経営リスク③:民事上の損害賠償責任
懲役または罰金も。労働安全衛生法に基づく罰則とは
今回の義務化に規定されている熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反となる可能性があります。
違反すると、事業者には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課されるおそれがあるため注意が必要です。
罰金だけではない、企業が負う3つの経営リスク
法的な罰則以上に、企業経営の根幹を揺るがしかねない3つの経営リスクが存在します。
- 1. 生産性の低下
- 熱中症は、従業員の集中力や判断力を低下させ、業務の生産性に直接的な影響を及ぼします。実際、暑熱ストレス下で作業する労働者の多くに生産性低下が認められるという報告や、気温上昇に伴う生産性の低下率が示されています。
- 2. 企業イメージの低下
- 「従業員の安全を守れない会社」という評判は、顧客離れや採用難に直結し、企業の持続的な成長を阻害します。
- 3. 損害賠償と事業停止のリスク
- 企業は従業員に対する安全配慮義務違反を問われ、多額の損害賠償を請求される訴訟リスクを負います。また、重篤な熱中症災害発生時には、労働基準監督署の調査により事業停止命令が下される可能性もあります。
参考:産業医学レビュー「職場における熱中症の現状と予防対策」
【義務化の内容】企業が取るべき3つの熱中症対策

企業が法改正に対応し、実効性のある熱中症対策を講じるためには、3つの柱が重要です。
具体的には、以下の3つの対策が求められます。
- 企業が取るべき3つの必須対策
-
- ● 対策①:緊急時に機能する「体制」の構築と周知
- ● 対策②:WBGT基準に基づく「職場環境」の管理
- ● 対策③:従業員を守る「健康管理」と「教育」
対策①:緊急時に機能する「体制」の構築と周知
まず取り組むべきは、もしもの時に迷わず行動できる体制を組織内に整備することです。
具体的には、めまいなどの初期症状を見逃さないための報告体制を明確に定め、周知します。
さらに、熱中症発生時の応急処置や救急搬送に関する「具体的な手順」を作成し、定期的な訓練を通じて誰もが実践できる状態にしておくことが重要です。
対策②:WBGT基準に基づく「職場環境」の管理
次に、客観的な指標を用いて職場環境を評価し、熱中症のリスクそのものを低減させます。その中心となるのが暑さ指数(WBGT)の活用です。
WBGTとは、気温だけでなく湿度や輻射熱(日光や設備からの熱)も考慮した、より実態に近い暑熱環境を示す指標です。具体的な管理方法は以下の通りです。
- ● WBGT値の測定と評価:市販のWBGT計で作業場所の数値を定期的に測定し、危険度を客観的に把握します。
- ● 基準に応じた措置の実施測定値に基づき、「作業を中断する」「休憩時間を増やす」といった社内ルールを明確に定め、確実に実行します。
- ● 環境改善設備の導入:スポットクーラーや遮熱シート、ミスト発生装置などを活用し、職場環境そのものを改善します。
対策③:従業員を守る「健康管理」と「教育」
最後に、従業員一人ひとりの健康状態に目を配り、予防意識を高める取り組みが欠かせません。
日常的な健康状態の確認はもちろん、科学的根拠のある予防策であるプレクーリング(事前の冷却)や暑熱順化(暑さへの順応)を計画的に導入します。
また、熱中症の危険性や予防法を学ぶ労働衛生教育を定期的に実施し、従業員の知識と自己管理能力を高めることは企業の重要な責務です。
同時に、従業員一人ひとりにも自身の健康を守る役割があります。十分な睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がける、前日の深酒を避けるといった基本的な生活習慣が、熱中症予防の土台となります。
企業が提供する対策と、従業員自身の健康管理が両輪となって、初めて実効性のある予防が実現します。
労働安全衛生教育のため、熱中症対策の基本を知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。
▼関連記事はコチラ
早めが肝心 熱中症対策
熱中症のメカニズムを解説 かかりやすい人や予防法は?
【ケース別】すぐに取り組める事業者の熱中症対策事例

熱中症対策は、企業の規模や業種によって課題が異なります。
中小企業ではコストを抑えた工夫、オフィスワークでは見落としがちなリスクへの配慮、外国人従業員に対しては言語や文化の壁を越えるコミュニケーションが必要です。
- ケース別の対策ポイント
-
- ● 中小企業:低コストで実践できる工夫
- ● オフィスワーク:見落としがちな屋内リスクへの対策
- ● 外国人従業員:言語・文化の壁を越える配慮
中小企業でも実践できる低コストな対策
大規模な設備投資が難しい中小企業でも、工夫次第で効果的な対策は可能です。
例えば、経口補水液や塩分補給タブレットの共同購入によるコスト削減や、従業員同士で水分補給を促しあう声かけ運動の実施など、低コストですぐに始められる取り組みから着手しましょう。
さらに、国の助成金を活用することも有効な手段です。例えば「エイジフレンドリー補助金」などは、高齢者を含む労働者のための熱中症対策設備(スポットクーラー、送風機、クールベストなど)の導入費用の一部を補助してくれます。
こうした制度を積極的に情報収集し、自社の負担を軽減しつつ、効果的な対策を進めましょう。なお、補助金制度は年度によって内容や申請期間が異なりますので、必ず厚生労働省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
参考:厚生労働省「令和7年度エイジフレンドリー補助金」のご案内
オフィスワークで見落としがちな熱中症対策
屋内だからと安心はできません。特に、節電意識からエアコンの設定温度を高めにしているオフィスでは注意が必要です。
サーキュレーターによる空気の循環や、ブラインドでの直射日光の遮断といった対策が有効です。
また、デスクワークに集中して水分補給を忘れがちになるため、時間を決めた休憩を促すことも大切です。
外国人従業員への特別な配慮とコミュニケーションの工夫
言語や文化の違いは、熱中症リスクを高める要因になり得ます。
母国が涼しい地域の出身者は日本の暑さに慣れていなかったり、体調不良を言い出しにくかったりするケースも想定されます。注意喚起の掲示物に、やさしい日本語やイラスト、多言語表記を用いるなどの情報伝達の工夫が重要です。
熱中症対策は専門家(産業医)との連携が成功のカギ
法令遵守と実効性のある対策を両立させるには、専門的な知見が不可欠です。
自社だけで対応が難しい場合は、産業医と連携することで、リスク評価から具体的な計画策定、従業員の健康管理まで的確な支援を受けられます。
自社だけでの対策に潜む落とし穴
熱中症対策の担当者が、他の業務と兼務しているケースは少なくありません。
専門知識が不足したまま手探りで進めると、法令の要件を満たせなかったり、現場の実態に合わない形骸化したルールになったりする恐れがあります。
担当者の負担が増え、本来の対策が機能しないという事態はできれば避けたいところです。
産業医に相談できることとは?体制構築から健康相談まで
産業医は、医学的な専門知識を持つ労働衛生の専門家です。
企業は産業医に対し、以下のような支援を受けられます。
- ● 職場巡視によるリスク箇所の客観的な評価
- ● WBGT値に基づく作業計画への専門的な助言
- ● 衛生委員会での議論の活性化支援
- ● 基礎疾患を持つ従業員への就業上の配慮に関する相談
熱中症対策に強い産業医の探し方と選び方
効果的な連携のためには、自社の業種や特性を深く理解してくれる産業医を選ぶことが重要です。
例えば、建設業や製造業など、現場での実務経験が豊富な産業医であれば、より実践的なアドバイスが期待できるでしょう。法令知識だけでなく、経営層や現場の従業員と円滑にコミュニケーションが取れるかどうかも、大切な選定ポイントです。
ワーカーズドクターズでは、嘱託産業医紹介サービスをご提供しています。専任のスタッフが自社の課題に最適な知識や経験を持つ産業医をマッチングし、初めての選任でも安心してご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。
嘱託産業医サービス | 産業医の紹介ならワーカーズドクターズ
企業の未来を守るため、3つの必須対策に今すぐ着手を
2025年6月からの熱中症対策義務化は、罰則回避のためだけではありません。
従業員の命と健康、そして企業の未来を守るための必要不可欠な経営課題です。
「体制の構築」「職場環境の管理」「健康管理と教育」という3つの必須対策は、すべての企業が取り組むべき土台となります。まずは自社の現状を把握し、計画的に準備を進めてください。