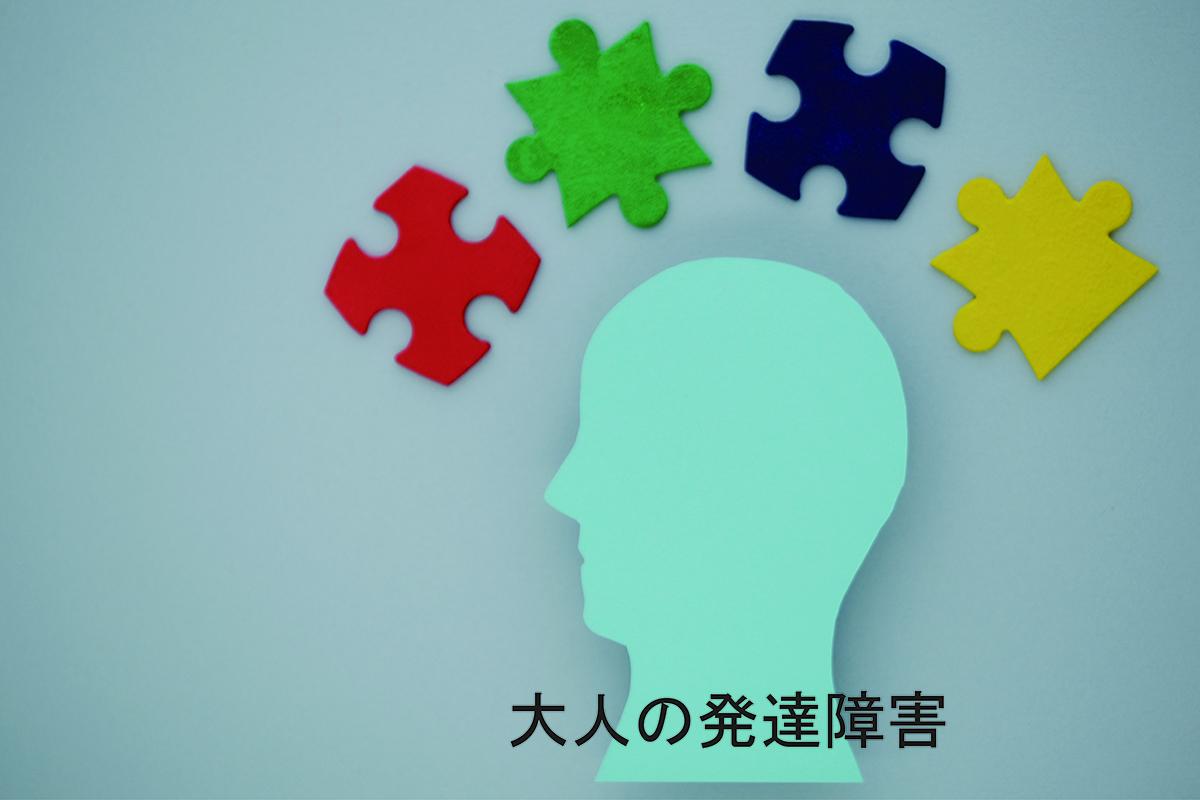【2025年4月から順次施行】育児・介護休業法の改正で働き方はどう変わる?
- 産業保健

2025年の育児・介護休業法の改正のポイントや、改正を踏まえて企業が対応しなければならないことについて解説します。
おすすめの資料
育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法の概要
育児・介護休業法とは、育児や介護が必要な家族を持つ従業員が、仕事と家庭生活(育児・介護)の両立をはかれるように支援することを目的とした法律です。
具体的には、育児休業では子どもが一定の年齢に達するまでの期間、介護休業では家族の介護が必要な場合に一定の期間、休業することができます。この制度により、従業員は育児や介護のために退職することなく、仕事と育児・介護を両立するための仕組みが提供されています。
【2025年施行】育児・介護休業法の改正の目的
今回の改正の目的は、育児や介護による従業員の離職を防ぎ、男女ともに育児・介護休暇をとりやすくするためです。
そのため、2025年4月から順次施行される改正後の育児・介護休業法では、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や育児休業の取得状況の公表義務の拡大、次世代育成支援対策の推進・強化をはかるとともに、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等がはかられています。
育児・介護休業法の改正が2025年4月から段階的に施行
2025年4月の施行では子どもの看護休暇の拡充や残業免除の対象拡大が進みます。また、2025年10月の施行では、フルタイム勤務と育児を両立させるための新しい制度の創設が行われるため、企業の体制整備が必要となります。
次の章では、これらの改正内容についてさらに詳しく説明していきます。
【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法の改正ポイント

2025年4月施行分の改正ポイント
2025年4月から施行される改正内容では、主に現行制度の拡充が中心となります。
- ①子の看護休暇の見直し【義務】
-
子どもの看護休暇を利用できる範囲を現行が小学校就学前の子どもであったのに対し、改正後は小学校3年生までに拡大され、学校行事に参加する等の場合にも取得できるようになります。
名称も看護に限定されないという意味合いから「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名称変更されます。また、これまでは勤続6か月未満の従業員は除外されていましたが、改正後は週3日以上勤務している従業員であれば取得可能となります。 - ②所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡充【義務】
-
子残業を免除される対象が育児や介護の状況にある従業員に拡大されます。対象範囲も3歳未満の子どもから小学校就学前へと制限が拡大され、ワークライフバランスを取りやすくなります。
- ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加【選択する場合は就業規則等の見直し】
-
フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営などに加え、テレワークも選択できるようになります。
- ④育児のためのテレワーク導入【努力義務】
-
3歳未満の子どもを養育する従業員のテレワーク導入は努力義務ですが、柔軟な働き方を実現するための措置のひとつとしてテレワーク(月10日)を選べる措置を講じる義務が企業側に生じるようになります。
- ⑤育児休業取得状況の公表義務適用の拡大【義務】
-
常時雇用者が300人を超える企業では公表する義務が生じます。
- ⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し】
-
介護休暇を取得できる労働者の要件として、勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みが廃止となります。
- ⑦介護離職防止のための雇用環境整備【義務】
-
介護休業や介護両立支援制度などの申請をしやすいように、介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施や相談窓口、制度利用に関する事例の収集や情報提供、制度の取得・利用促進に関しての方針を周知するなどの措置を講じる必要があります。
- ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】
-
介護に直面する前の早い段階(40歳など)に、制度等に関する情報提供を面談か書面で行う必要があります。
- ⑨介護のためのテレワーク導入【努力義務】
-
要介護状態の対象家族を介護する労働者の働き方として、テレワークを選択できるように就業規則等を見直す必要があります。
2025年10月施行分の改正ポイント
10月施行分の改正ポイントは以下の通りです。
- ①柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】
-
3歳から小学校就学前の子どもを療育する労働者は、柔軟な働き方を実現するために、始業時刻の変更やテレワーク、短時間勤務、療育両立支援休暇の付与、その他の措置のうち2つを選択するなどの具体的な措置を講じる必要があります。
- ②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
-
育児休業後に復職する際や勤務形態を変更する際に、従業員が希望する勤務スタイルやサポート内容について、企業担当者が事前に聴取する場を設ける必要があります。
意見を聴いたうえで、フルタイム勤務だけではなく、時短勤務などの柔軟な勤務時間・勤務形態を導入したり、在宅勤務やテレワークを導入したりなど、複数の選択肢を提示し、仕事を続けられるように配慮をする必要があります。
【育児・介護休業法】改正を踏まえ企業が対応すべきこと

就業規則・労使協定の見直し
育児・介護休業法の改正に伴い、企業は就業規則や労使協定の見直しを行う必要があります。とくに育児・介護休業の取り扱いについて、育児休業や介護休業の取得期間、給与などの取り決めを見直し、改正内容を就業規則に反映させましょう。
また、復職後の勤務形態の変更などに関する規定の見直しも必要です。就業規定等の変更後は従業員への周知も重要です。従業員が自分の育児や介護に関する希望を伝えやすく、企業側もその意向を反映させた柔軟な対応ができる体制を整えましょう。
育休取得状況の調査と従業員数の把握
育児・介護休業法の改正により、2025年4月から従業員数が300人を超える企業に対しても、男性の育児休業取得状況を公表することが義務化されました。
そのため企業は自社が公表義務の対象なるか従業員数をしっかりと把握しなければなりません。公表義務の対象である場合、「育児休業等の取得割合」と「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」から従業員の取得状況を確認し、事業年度ごとの公表が必要です。
なお、従業員数は以下の「常時雇用する労働者」の数で把握します。
従業員への変更点の周知
規約や社内制度を変更・更新した場合には、社内での研修や説明会を実施してその内容を従業員全体に周知しましょう。社内掲示板やイントラネット等を活用して、従業員全員に確実に伝えることが重要です。また、就業規則や労使協定を変更した場合も、変更内容を明記した文書を配布するなど、従業員がいつでも確認できるようにしておきましょう。
まとめ:育児・介護休業法の適切な運用のため、早めの体制整備を!
育児・介護休業法の改正により、企業は就業規則や労使協定の見直しなどさまざまなニーズに応えるために体制整備を行う必要があります。体制整備を早めに進めることで、育児、介護に伴う離職を減らし、従業員のモチベーションや生産性を向上させることができれば、企業としてもメリットは大きくなります。
会社全体でさまざまな働き方やライフステージの変化を理解して、柔軟に対応していきましょう。
おすすめの資料